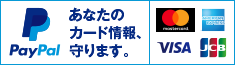糸島めんま(国産めんま)

糸島めんまのスタートは、放置竹林から純国産のめんまを作ろうと平成26年から試作を開始、28年から試験的に販売を開始しました。自社の本業はデザイン制作ですが、ひとりの農業者として放置竹林の整備や竹パウダー・めんま作りを行いました。
糸島めんまの名称で「メンマ」を使わないのは、私が保健所に登録に行った際にメンマと呼ぶにはこのような製法で作らないといけないと書類を見せられました。登録は「糸島タケノコの塩漬」になりましたので、メンマを使わず愛称として「糸島めんま」とひらがなで呼ぶことになりました。各地のみなさんも地域性のある名称にしてみてはいかがでしょうか。
タケノコは採るだけではダメです。親竹を残しながら整備しないと細い竹しか生えなくなります。適期に整備し、たい肥まで入れると放置竹林がタケノコ畑になります。
現在、全国で国産めんまづくりが始まっています。安心安全な国産のタケノコを食べることで放置竹林の整備が徐々に進んでいます。
残念ですが私は病気のため糸島めんまの製造販売を断念することになりました。今後はできる範囲で整備し自宅で食べる分を作ります。整備をさぼると元の竹藪にもどりますから…。
各地でタケノコの特産品が生れることを期待しています。頑張ってください。(R3.12)